human and environment
3-2. 定義
- 環境汚染 - 松田 八束
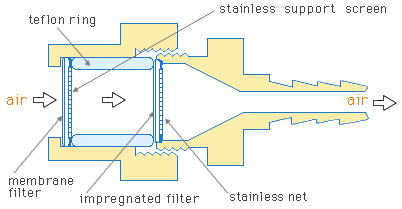
エアロゾル(aerosol)気体中に固体もしくは液体の粒子が分散しているもの。通常、エアロゾルは少なくとも数秒間程度は安定状態を保っているが、ときには1年もしくはそれ以上にわたって安定状態を保っている場合もある。エアロゾルという言葉には、粒子を分散させている気体(通常は空気である)をも含んでいる。粒子の大きさは0.001μmから100μm以上までの範囲である。
関連語:空中分散粒子系(aerodisperse system)
- 通俗的な呼称
-
粉塵(dust)
固形物がその化学的組成を変えず、形、大きさが変わって粒状になり空気中に分散したもので、粉砕、研磨、穿孔、爆発など、主として物理的破砕過程で生じる。球形、針状、薄片状など、形、大きさともに不均一でかつ大きさは1μm以上のものが多く、サブミクロンから目に見えるものまである。
フューム(fume)
固体が蒸発してのち凝縮して粒子となったもので、金属の加熱溶融、溶接、溶断、スパークなどの際に生じる。蒸気またはガス状の燃焼生成物が、凝縮して生成する固体粒子のエアロゾルも含む。このような粒子の生成過程では、一般に物理的作用に化学的作用が加わり、空気中では多くの場合酸化物となっており、球状か結晶状である。粒径は小さく1μm以下のものが多い。
煙(smoke)
燃焼の場合に生じるいわゆる“けむり”に類するもので、一般に有機物の不完全燃焼物、灰分、水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒子は球形に近いが、これらが凝集してフロック状をなすものが多い。通常、直径1μm以下の大きさである。
煙(smoke)
燃焼の場合に生じるいわゆる“けむり”に類するもので、一般に有機物の不完全燃焼物、灰分、水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒子は球形に近いが、これらが凝集してフロック状をなすものが多い。通常、直径1μm以下の大きさである。
ミスト(mist)
一般には微小な液体粒子を総称していう。液体が蒸発凝縮したもの、液面の破砕や噴霧などにより分散したものがすべて含まれ、形状は球形である。粒径は生成過程の差異によってかなり幅がある。サブミクロンから約20μmまでの広がりをもつ。
粗大粒子(coarse particle)
直径2μm以上の粒子
微小粒子(fine particle)
直径2μm以下の粒子
- 気象学の分野における大きさに着目した分類
-
エイトケン粒子(Aitoken particle: 0.001-0.1μm)
大粒子(large particle:0.1-1μm)
巨大粒子(giant particle:1-100μm)
参考文献:
駒林 誠、「気象の科学」NHKブックス196、日本放送協会、昭和50年11月1日第4刷
- 地表付近の気象、塵象における用語
-
霧(fog)
ごく小さな水滴が大気中に浮かんでいる現象で、水平視程が1km未満のもの。目に見えるミスト。
霧(mist)
霧と同様であるが、水平視程が1km以上のものをいう。
煙霧(haze)
ごく小さな乾いた粒子が大気中に浮かんでいる現象で、黒っぽい背影では青紫色がかり、明るい背影では黄褐色にみえる。同様な現象であっても汚染源が明らかな場合は煙とし、そうでないときを煙霧とすることがある。
スモッグ(smog)
smokeとfogからなる合成語である。その内容についての明確な定義はなく、煤煙で汚れた霧というくらいの意味である。「光化学反応による生成物であり、通常、水蒸気と結合している。」と定義される場合もある。粒子は、通常1-2μm以下である。
Los Angels型スモッグ
石油系燃料による煙霧と煙とから生じる大気汚染現象
London型スモッグ
石炭系燃料による煤煙と霧とから生じる大気汚染現象
クラウド(cloud)
はっきりした境界面を有する目に見えるエアロゾル。
- 我が国における大気汚染関係の用語
-
ばい煙
いおう酸化物、煤煙、その他の有害物質
粉塵
物の破砕、選別その他の機械的処理または堆積に伴い発生し、または飛散する物質でダストともいう。また気体中に浮遊しているものを浮遊粉塵という。
浮遊粒子状物質
大気中に浮遊する粒子状物質であって粒径が10μm以下のもの。
生物系エアロゾル粒子
花粉、胞子などが気体中に浮遊しているもの
- 一般に、上記の区別は必ずしも必要としないので、一般的な言葉であるエアロゾルを用いる。固体粒子はparticle、液体粒子はdropletと呼ばれる。粒子状物質(particulate matter)という言葉は、固体粒子、液体粒子のどちらでもあてはまる。1次エアロゾル(primary aerosol)は、大気中に直接放出された粒子を含有するものであるのに対し、2次エアロゾル(secondary aerosol)は気体成分の化学反応(気体−粒子変換)によって大気中で生成された粒子を含有するものである。
単分散(monodisperse)エアロゾルは、粒子がすべて同じ大きさのものである。これは試験用エアロゾルとして実験室でつくられる。多分散(polydisperse)エアロゾルは、ある範囲の粒径の粒子から成っており、きわめて広い粒径範囲を示すことが多い。その大きさを特性づけるには、統計的な計測が行われなければならない。
ここでは、標準状態を温度20℃、圧力760mmHgの状態と定義する。